HSPや発達障害の仕事における悩みと無理なく支援する方法は?

HSPとは、生まれつき5人に1人は当てはまる、繊細で敏感な気質の人を指します。
また、発達障害は、HSPと異なり、病院などで「障害」として認められる生まれつきの特徴です。
HSPと発達障害は、「生まれつき」という部分で一致するものの、特徴は全く異なります。(HSPの詳細や発達障害との違いの詳細については、下記リンクからご参照ください。)
「HSP」と「大人の発達障害」の似ている点は?相性や決定的な違いも
ただ、仕事の中で感じる「生きづらさ」や「働きづらさ」は、HSPと発達障害で似通っている部分があります。
そして、職場のメンバーに理解されづらいという点についても、共通している部分があります。
HSPや発達障害は、テレビや本などの大型メディアに取り上げられているのにも関わらず、TwitterなどのSNSの場では「周囲の人が理解してくれない」「周囲の人に理解してほしい」という意見を散見しており、実際の職場においても適切な支援がなされていることはとても少ないです。
そのため、職場での理解や支援がなされるためには、職場のリーダーの雰囲気作りがとても大事になってきます。
恐らく、職場のリーダーの方は、特定の人に配慮することは大変だし、他のメンバーたちのメリットにもつながらないと思っている人が多いのではないでしょうか。
でも、とある考え方をすることで、特定の人への配慮が、他のメンバーたちのメリットにもつながり、職場全体の雰囲気が良くなったり、生産性が高まったりすることもあります。
そこで、今回は職場のリーダーの方に向けて、HSPや発達障害の仕事における悩みと無理なく支援するための方法を伝えていきたいと思います!
ぜひ、最後までご覧ください。
この記事の目次
HSPや発達障害の人の仕事における悩みが理解されない理由とは?
(1)HSPや発達障害の人の仕事における悩みが職場に理解されない理由

HSPや発達障害の人が、仕事で困難を抱えている理由…それは、周囲に悩みを理解してもらえないことに多くが起因しているためです。
HSPや発達障害の人の悩みが、周囲に理解してもらえない理由については、以前に以下のとおり考察しました。
| 【HSPや発達障害の人が周囲に理解してもらえない理由(ブログ主の考察)】 ・人にとって一番大事な存在は自分だから ・HSPによる生きづらさは目に見えるものではないから ・生きづらさを他人に理解してもらいたいのはHSPの人だけではないから ※詳しくは、こちら(本ブログの過去記事)からご参照ください。 |
そして、日本では、他国と比較すると、HSPや発達障害といった概念は広く知られづらい状況にあります。
それは、下記の理由のとおり、日本では「普通」ということを重要視する文化にあるためです。
アメリカとの対比になりますが、異なる民族が入り混じった社会では、言語を中心とした文化に関する共通理解というものは、互いにほとんどないのが前提になります。ひるがえって日本では、島国という特性上、言葉はもちろんのこと、自分たちが育った環境に対する常識というものが、日本国内のどこに行っても通用して当然という前提があります。
(中略)
日本人にとって、欧米人の「神との契約」に相当するほどに行動を規定するもの、それは横の関係すなわち「人と人との間」に存在します。欧米人が神の教えに倫理的配慮を行なうのに対して、私たち日本人は世間の感覚に対して倫理的配慮をしながら、自らの行動の意思決定を行なっているのです。
引用:中西康介(2017)『家族と向き合う不登校臨床―保護者の積極的な関わりを引き出すために』誠信書房
だから、日本の教育や仕事の現場を見てみると分かるとおり、没個性的(個性を重要視しない)な考え方が強い状況にあります。
もちろん、没個性化によって私たちはたくさんのメリットを受容しているわけですが、その一方で、生まれつきの気質や自分の力で変えづらい性格はなかなか周囲に理解されにくく、「生きづらさ」を抱える人が多くいるのも確かです。
ただ、職場のリーダーの人の立場としては、たくさんの人を見なければいけない立場として、メンバー一人ひとりの悩みを理解していく…というのは、どうしても時間的制約上、難しいことだと思います。
それでは、職場のリーダーの人の立場として、メンバー一人ひとりの悩みに対して効果的にアプローチしていくための考え方を紹介したいと思います。
(2)HSPや発達障害の人に無理なく支援する考え方

さて、先ほどまでは、HSPや発達障害の仕事などでの悩みが周囲に理解されづらい理由を述べてきました。
そして、職場のリーダーの立場として、メンバー一人ひとりの悩みを理解していく…ということが難しいということも述べてきました。
それでは、職場のリーダーの立場として、HSPや発達障害の人に無理なく支援するためには、どのように考えていけば良いのでしょうか。
そのヒントとなるのが、「ユニバーサルデザイン」の考え方です。
「バリアフリー」と誤用される考え方でもありますので、その違いについて、下記のとおり示したいと思います。
| ・バリアフリー…お年寄りや障害のある方といった特定の人を対象として、快適に生活できるように、後からバリア(障壁)をなくすこと ・ユニバーサルデザイン…国籍や性別、年齢、そして障害があるかないかなどに関係なく、初めから、全ての人ができるだけ使いやすいものを広めることです。 ※ユニバーサルデザインは全ての人を対象にするため、特定の人の専用品となるバリアフリーに比べると対象者が広くなります。一般的には、バリアフリーを一歩進めた考え方がユニバーサルデザインと言われ、広い意味ではユニバーサルデザインにバリアフリーが含まれる場合もあります。 引用(一部改変):福津市ユニバーサルデザイン「ユニバーサルデザインとは」(2019年7月7日アクセス) |
ここでわかるとおり、「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」の違いについて、「バリアフリー」は特定の人の配慮である一方で、「ユニバーサルデザイン」はすべての人へのメリットにつながるというわけです。
特定の人への配慮である「バリアフリー」は、自分にとって関係ない人からしてみれば、どうしても受け入れられない場合があります。
だけれども、すべての人へのメリットにつながる「ユニバーサルデザイン」であれば、職場全体としてのメリットにもつなげられる可能性があるというわけです。
「ユニバーサルデザイン」の原則としては、下記のとおり考えられています。
【ユニバーサルデザインの7原則】
●公平性
使う人がだれであろうと、公平に操作できること。できるかぎり、すべての人が、いつでもどこでも、同じように使いこなすことができる。●自由度
使用するときの自由度が高いこと。たとえば、右ききの人でも、左ききの人でも、思いどおりに使える。●カンタン
使い方がとっても簡単であること。ひと目見ただけでも、すぐに使い方が理解できるわかりやすい作り。●明確さ
わかりやすい情報で理解しやすいこと。使う人の知りたいことが、わかりやすくていねいに説明されている。●安全性
使うときに安全、安心であること。うっかりミスで、まちがった使用をしても、できるかぎり危険につながらない。●持続性
使用中からだへの負担が少ない、少ない力でも使用ができること。長い時間使っても、どんなかっこうで使用しても、疲れにくい。●空間性
だれにでも使える大きさ、広さがあること。使う人の大きさや、姿勢、動きに関係なく、ラクに使いこなすことができる。引用:KOKUYO「ロン・メイスの7原則」(アクセス日:2019年7月7日)
「ユニバーサルデザイン」は、形あるものに対して、適用されることが多い考え方です。
でも、この考え方は、自分の仕事における悩みといった、形のないものに対しても適用できると私は考えています。
私は、「ユニバーサルデザイン」の考え方に基づき、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」を追い求めることで、無理のない支援につながるのではないかと思います。
それでは次に、HSPや発達障害の人の仕事における具体的な悩みと、「ユニバーサルデザイン」の考え方に基づく支援の方法をお伝えしていきたいと思います。
スポンサーリンク
HSPや発達障害の仕事における具体的な悩みと無理なく支援する方法とは?
悩み①:遅刻が許されないプレッシャーで眠れない

| 【Twitterなどで寄せられたHSPや発達障害による仕事の悩み】 時間を決められるのが苦手で、遅れてはダメだというプレッシャーのために、前日よく眠れないことがある。好きな時間に出社可能な仕事がこの世界に存在してほしい… |
最近は、出社・退社の時間を選べる「コアタイム制度」をとっている会社が増えてきました。
それは、起きるのが苦手な人がいるから…という理由というよりは、育児や介護などの関係で、やむを得ず出社や退社時間を選ばなければいけない人も多いからです。
とはいえ、目の前の人を相手にするサービス業などでは、職場のリーダーの立場として、メンバーに出社・退社時間を選んでもらうことが難しいという場合もあると思います。
さて、決まった時間に起きることが苦手な人は、「起きる時間と寝る時間が一定していない」ことが多いと言われます。
そこで、決まった時間に起きるためには、「起きる時間と寝る時間を一定させる」ための努力が重要になってきます。
職場のリーダーとして、無理なく支援するためには「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」だと述べました。
この考え方に基づき、このように対応すれば、職場全体のメリットにつながるのではないでしょうか。
| 【職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援(例)】 ・(特に交代制の職場環境であれば)起きる時間と寝る時間を一定させる重要性をメンバー間で共有する ・職場で、出社時間と退社時間についてアンケートをとる ・アンケートに基づき、無理のない範囲で、出社・退社時間を調整する |
こうすれば、「朝決まった時間に起きることが苦手」な人のみならず、「育児や介護を理由に出社・退社時間をずらしたい」人などへの支援もできるわけです。
このような対応をとれば、長期的な離職率への解決や優秀な人材の採用などにもつながり、職場の環境が良くなり、生産性の向上などにもつながるのではないかと思います。
悩み②:自分の能力や進捗に応じて仕事を振ってほしい

| 【Twitterなどで寄せられたHSPや発達障害による仕事の悩み】 仕事を振られたときに断るのが苦手です。他の仕事を抱え込んでいるときもあり、リーダーの立場の方には、もっと一人ひとりの能力や作業量を把握してほしい… |
これも、よく散見する意見ですね。
リーダーの立場としては、職場のメンバーに対して仕事を振ったときに、仕事量が多いのであればその場で断ってほしい…と思う気持ちはよく理解できるのですが、目上の立場から仕事を振られたときに断るというのは、結構キツいと思っている人が多いのも確かです。
限られた時間の中で、一人ひとりの能力や作業量を把握することはとても難しいですが、実はこれを把握していないと、職場のメンバーが異動・退職したときに、引き継ぎが大変になってしまうなどといったデメリットが発生します。
そこで、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」としては、次のとおり考えられます。
| 【職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援(例)】 ・定期的(例:週に一度)に、仕事の進捗を職場のメンバー間で報告し合う打合せの場を設ける ・職場の各メンバーの仕事をまとめたシート(WBS(※)など)を用意し、進捗報告の打合せの前に各メンバーに記入してもらう (※)WBSは、Work Breakdown Structureの略です。インターネット等で作成方法を調べることができます。 |
リーダーひとりで、職場のメンバー全員の、仕事の能力や進捗を把握するのはとても難しいです。
というのも、特に仕事の進捗については、日々変化するものだからです。
そのため、職場のメンバーに進捗共有を手伝ってもらうことがとても重要になります。
そこで、進捗報告の機会として打合せの場やシートを用意すれば、メンバーの協力行動を誘発できるというわけです。
しかも、仕事の進捗を共有することで、職場のメンバー間で協力し合う雰囲気も作れるかもしれません。
このようにすれば、職場のリーダーの立場として無理をしなくても、メンバー一人ひとりの仕事の能力や進捗を把握でき、仕事の割り振り方も不満が出ないようにできるのではないでしょうか。
悩み③:電話などが気になって目の前の作業に集中できない

| 【Twitterなどで寄せられたHSPや発達障害による仕事の悩み】 私の職場は、突然の電話、来客、打ち合わせや相談があり、自分だけで集中して仕事をする時間がなかなか取れません。1日に2時間とか、1人でこもって集中できる個室の仕事部屋がほしい… |
HSPや発達障害の人は、マルチタスクが苦手です。
だから、電話や来客、打合せなど、作業を中断されることで、仕事の効率は格段に落ちてしまいますし、ミスを誘発します。
ただ、HSPや発達障害の人に限らず、マルチタスクを強いることは生産性を妨げたり、更には脳に悪い影響を与えたりといったことが各所で報告されています。
そこで、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」としては、次のとおり考えられます。
| 【職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援(例)】 ・職場の中に、作業部屋や作業スペースを作る ・職場全体の仕事が滞らず、作業部屋や作業スペースの利用条件を公平にするために、予約制などのルールを決める |
こうすれば、職場のメンバー全員のメリットにつながる施策とできるのではないかと思います。
悩み④:蛍光灯の光が強くて体調不良になる

| 【Twitterなどで寄せられたHSPや発達障害による仕事の悩み】 私の職場はHSPが苦手な要素満載なのですが、一番辛かったのは蛍光灯の光です。蛍光灯の白い光が本当にツラくて、オレンジっぽい暖かい色にしてほしい… |
HSPや発達障害の人の一部においては、強い光に敏感です。
そのため、こういった意見をよく見聞きすることがあります。
実は、この点については、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」を考えることに一番悩みました。
ただ、照明のあり方というのは、職場の生産性に大きく左右することがわかっています。(外部リンク:Offive&Co.「オフィスの照明が眩しすぎて苦手な人へ。明るさの本当のお話。」を参照)
研究などでは、照明が明るすぎるのも良くないですし、作業のシーンによって適している照明の明るさや色が違うことも分かっています。
そこで、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」として、次のとおり考えます。
| 【職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援(例)】 ・作業部屋など、特定の部屋に調光可能な照明を用意する。 |
建物の全体管理の関係で、オフィスで照明の明るさや色が決まっている職場も多いと思いますし、人によっても、自分に適した明るさが変わってくると思います。
そこで、先ほどの悩み③も踏まえて考えてみると、特定の部屋(作業部屋など)に調光可能な照明を用意するということが考えられるのではないでしょうか。
照明が調光可能であることで、一人ひとりに合った明るさが実現可能ですし、特定の部屋に限定すれば全員に特定の照明の明るさと色を強制することもないですし、職場の生産性の向上にもつながるのではないでしょうか?
悩み⑤:自分がいないところでの職場の陰口が気になる・打合せスペースが無くて相談しづらい

| 【Twitterなどで寄せられたHSPや発達障害による仕事の悩み】 その場にいない人を批判するのを聞いているのは、やっぱり苦手です。そのような言動が離職につながっていることをトップダウンで浸透させてほしい… 込み入った相談などをするときに、パーテーションか何かで区切られた打合せスペースが充実してほしい… |
さて、寄せられた悩みの2つをまとめさせていただきました。
この2つの悩み、一見似た悩みに見えないかもしれません。
でも、実は大事な共通点が隠されているのです。
それは、本音を言ったり、相談しづらかったりする雰囲気が職場にあると思うのです。
後に説明しますが、職場の生産性や雰囲気を良くするにあたって大事である「心理的安全性」にも大きく関わる要素でもあります。
職場のリーダーとしては、HSPや発達障害の人に限らず、職場の人たちが本音を言ったり相談をしたりしやすい雰囲気を構築することがとても大事なのです。
ということで、「職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援」として、次のとおり考えます。
| 【職場全体のメリットにもつながるHSPや発達障害の人への支援(例)】 ・職場の人が相談しやすいスペースや時間(機会)をつくる ・職場のメンバーがフラットに話し合えるランチなどの機会をつくる |
特定の人へ支援することは、職場全体の生産性を落とすと思われることもあります。
しかし、考え方を変えれば、特定の人への支援を通じて、職場全体の生産性を高めることもできるのです。
そして、その中でも一番大事なのは、ここで紹介したとおり、「心理的安全性」を高め、悩みや本音を言い合える雰囲気作りが、職場のリーダーとしてはとても大事になります。
ということで、最後に、この「心理的安全性」について、お話ししたいと思います。
スポンサーリンク
職場のメンバー個々の悩みに対応することは生産性の向上にもつながる

さて、これまでHSPや発達障害の人の悩みにうまく対応することで、職場全体の雰囲気の向上や生産性の向上につながると言ってきました。
これは、HSPや発達障害の人に限る話ではありません。
HSPや発達障害以外の気質で悩みを抱えている人もいるし、どんな人だって悩みを抱えるものなのです。
職場のリーダーとしては、メンバー個々の悩みを職場全体のメリットにつながるようにすれば、良い職場の雰囲気を醸成できるわけです。
とは言っても、職場のリーダーは時間が限られているため、一人ひとりの悩みを聞いている余裕ありません。
そのため、大事になるのは、メンバーのみんなが本音や悩みを言えるような、状況をつくることなのです。
ここで鍵になるのが、「心理的安全性」ということになります。
「心理的安全性」については、下記のとおり、解説がなされています。
心理的安全性とは、「psychological safety(サイコロジカル・セーフティ)」という英語を和訳した心理学用語で、チームのメンバー一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言・行動できる状態のことを指します。より身近な表現として、「チームの中で自分が自分らしく働いている状態」や「安心して何でも言い合えるチームだと感じる状態」と言い換えることもできます。アメリカGoogle社のリサーチチームが「効果的なチームを可能とする条件は何か」を見つける目的で行った「Project Aristotle」というプロジェクトの研究結果として、心理的安全性が生産性の高いチームづくりに最も重要であることを発表して以来、国内外で心理的安全性が注目されるようになりました。
引用:ダイレクト・ソーシング・ジャーナル「心理的安全性の作り方・測り方。Google流、生産性を高める方法を取り入れるには」(アクセス日:2019年7月8日)
職場のリーダーとしては、生産性を高めることを日々求められると思いますが、そのためには「心理的安全性」を高めることが大事だと言うわけです。
そして、職場のリーダーとして、心理的安全性を高めるためには、下記のことを留意すべきと考えられています。
【心理的安全性を担保するための基本的な考え方と手法】
①発言機会を均等に与える
②競争よりも協力を促す
③ポジティブ思考を意識する
④上司が部下を尊重する
⑤価値のある1on1を実施する
⑥腹を割って話すきっかけを作る
⑦新人をチームとしてサポートする
⑧評価方法を見直す
⑨風通しの良い組織を作る
⑩チーム編成を見直す【心理的安全性を高める際の注意点】
①馴れ合うだけの関係にしない
②上司としての役割を忘れない引用:ダイレクト・ソーシング・ジャーナル「心理的安全性の作り方・測り方。Google流、生産性を高める方法を取り入れるには」(アクセス日:2019年7月8日)
これらを簡単にまとめると…
仕事に対する厳しさは残しつつも、本音や悩みを言い合う・聞き合う環境を作る。
そして、決して独りよがりになったり、他人を出し抜いたりすることを避けるようにすることが大事だと言えると思います。
恐らく、「心理的安全性」が高まることで、これまで紹介してきたHSPや発達障害の人をはじめとして、他人が抱える本音や悩みを職場のメンバー個々が理解し、協力し合い、それが結果的に職場の生産性につながるのではないかと思うのです。
そして、たったひとりの悩みをきっかけに、職場全体の良い雰囲気や生産性の向上につながる可能性を秘めている…だからこそ、職場のリーダーは、職場のメンバーの悩みに真剣に立ち向かってほしいと思うのです。
スポンサーリンク
まとめ
●HSPや発達障害の人の仕事における悩みが理解されない理由とは?
●職場のメンバー個々の悩みに対応することは生産性の向上にもつながる!
|
スポンサーリンク
おわりに

さて、今回の記事はいかがでしょうか。
今回は初めて、HSPや発達障害が周囲にいる方向けに記事を執筆しました。
HSPや発達障害などの生まれつきの気質によるツラさは、周囲から理解されづらいため、それが「生きづらさ」に直結しやすい状況にあります。
だからこそ、少しでも、周囲から理解が寄せられれば、その気質が長所として活かせる可能性もあるわけです。
でも、どうして、周囲から理解されづらいのか?
究極言ってしまえば、理解しても自分にメリットがないと考える人が多いからなのではないでしょうか。
これは弱者に対する、対応に通ずる考え方でもありますが、確かに短期的に見れば、弱者は切り捨ててしまった方が短期的な生産性は高まるかもしれません。
でも、切り捨てが続いてしまうと、その次の弱者が切り捨てられ、チームが崩壊するまで、切り捨てが続いてしまうこともあるのです。
なので、チームの良い雰囲気を醸成するためには、切り捨てが起きないように、協力的な雰囲気を醸成した方が良いと思うのです。
それが、結果的には、長期的な職場の生産性の向上にもつながるとも思うのです。
だからこそ、今日は、職場のリーダーに向けて、弱者に支援することはメリットにもつながるということを理解いただきたく、記事を執筆して参りました。
それでは、今回はこの辺で終えたいと思います。
もし、悩んでいる方にとって、少しでもお役に立てたのであれば、大変幸いです。
それでは、また次回も、よろしくお願いいたします!
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



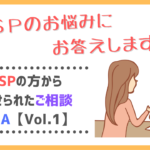
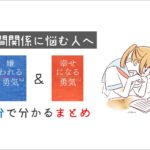
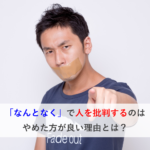
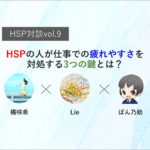
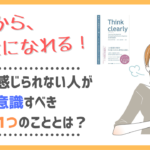


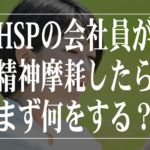
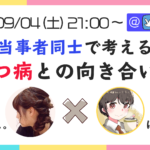

この記事へのコメントはありません。